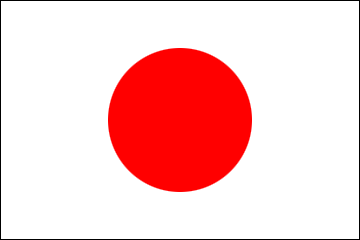北野大使によるダブリン・シティ大学(DCU)における日本人留学生への講演 (2019年11月14日)
令和元年11月18日
(はじめに)
皆さん,本日はお忙しい中,お集まりいただき,ありがとうございます。今,紹介をいただいた北野です。本日,DCUに留学しておられる日本の学生の方々にお話しする機会をいただき,大変うれしく思います。私は,アイルランドに駐在する日本の大使として,アイルランドの情勢を把握し,日本とアイルランドの関係を増進させる仕事に当たっています。そうしたことから,本日は「日本,アイルランド,将来キャリア」というテーマを選ばせていただきました。三部構成でお話しさせていただきます。まず「日本から見るアイルランド」についてお話しし,次に「アイルランドから見る日本」について触れた上で,「アイルランド滞在をどのように将来キャリアに生かすか」についてお話しさせていただければと思います。
(日本から見るアイルランド)
日本から見て,アイルランドはどのような特徴を持った国でしょうか。どのような点が注目点なのでしょうか。多くの答えがありうるかと思います。「フレンドリーな英語国」「スポーツ大好きの国」といったことも思い当たりますが,今日は,四つの視点を取り上げたいと思います。
第一が,「生活の質とダイナミズムを高いレベルで両立している国」という点です。少し解説させてください。生活の質とダイナミズムを両立させるということはどの国にとっても容易ではありません。日本のことを考えてみると,1950年代半ばから1970年代初めまでが高度成長期でした。この時期は,まさにダイナミズムの時期であり,それとともに,生活の質が大きく向上しました。その後の時期も経て現在では,日本における生活の質は非常に高くなっています。一方,かつてのようなダイナミズムを維持することは難しくなっています。これは日本だけの現象ではありません。多くの先進国が同じような経験をしてきています。経済成長を経て生活の質が高まり,成熟社会に向かうにつれて,ダイナミズムを維持することは難しくなるのです。中国も,今,そのような時期にさしかかってきているのではないかと言われます。
そのような中,アイルランドは,生活の質とダイナミズムを高いレベルで両立させている国です。生活の質について,一人当たりGDPを見てみると,78,335ドル(2018年)です。これは,世界第5位の数字です。ちなみに,日本の一人当たりGDPは,39,304ドルですので,アイルランドの数字は日本の約2倍です。ダイナミズムについて,GDP成長率を見てみると,2018年で8.3%となっています。先進国は軒並みどこも低成長となっているので,これは,先進国の中で飛び抜けて高い数字です。ちなみに日本の2018年の数字は0.8%です。
もちろん,アイルランドは,日本に比べれば小さな国です。人口で見れば27分の1,面積で見れば5分の1,経済規模で言えば13分の1です。一方,どの国にとっても大きな課題となる「生活の質とダイナミズムを高いレベルで両立させる」ということを可能にしているということは注目に値します。
なぜ,アイルランドではそれが可能になっているのか。私の考えでは,いくつかの要因があるかと思います。一つは,外資の役割,二つ目は,教育・人材育成の充実,三つ目はオープンな国柄です。日本としても学ぶところが多い国と思います。
アイルランドの特徴の第二の点として,「国際社会における注目国」ということを挙げたいと思います。10月には,連日,世界中で英国のEU離脱についてのニュースが取り上げられました。多くの方がご存じと思いますが,英国のEU離脱において,アイルランドは鍵を握る国です。2016年6月に英国で国民投票があり,翌2017年から英国とEUとの間の交渉が本格化しましたが,最大の焦点となったのが,アイルランド国境をどのように取り扱うかでした。これには,アイルランドと英国に属する北アイルランドとの間で現在,事実上,国境を意識することなく行われている経済活動をどうするのかという問題と,かつて1960年代後半から1998年まで30年以上続いた北アイルランド紛争の再燃をどう防ぐかという二つの問題が絡んでいます。アイルランド国境を「摩擦のない国境」として維持するという要請と,EU離脱を実現するという要請をどのように両立するかがこの交渉における最大の懸案となってきました。世界の注目がアイルランド国境の問題に向けられてきました。英国が総選挙に突入したので,この交渉はまだ決着に至っておらず,現在進行形のものです。
国際社会における注目ということからすると,先ほども触れた北アイルランド紛争についても申し上げたいと思います。現在,世界には,多くの紛争が起こっています。シリア,イエメン,リビア,ウクライナ,ジョージア。紛争地域を挙げようとすると,長いリストになってしまいます。このようなことから,紛争解決,平和構築というのは,国際社会において,常に重要な課題になっています。そうした中,北アイルランド紛争は,30年以上続き,約3600人もの方が亡くなったという深刻な紛争でしたが,長年の和平努力を経て1998年のベルファスト合意によって紛争に一応の終止符が打たれた事例であり,紛争地域の関係者の方々が,紛争解決,平和構築のために参考にしようとする事例となっています。
北アイルランドでは,かつてのような流血の連鎖は止んでいるものの,依然として多くの課題を抱えているのも事実です。一方,そうしたことを含めて,アイルランドは紛争解決,平和構築に取り組もうとする人の関心を集める場所となっています。
アイルランドの注目点の三番目として,「歴史から政策が作られる国」という点を挙げたいと思います。どの国にとっても,どのような政策をとるかは,その国の歴史的な歩みが影響を与えるということが多かれ少なかれ言えるかと思いますが,アイルランドは,それがはっきりと見える国の一つではないかと思います。アイルランドの外交方針の一つは,「軍事的中立政策」です。軍事に重きを置かない。軍事同盟に参加しない。戦争への加担を避ける。そうした方針でやってきました。これらは,おそらく自らが長年の間,支配されてきた「英国」へのアンチテーゼという観点から理解することができるのではないかと思います。
アイルランドは,また,貧困軽減,難民への対応といった問題で,できる限り前向きの対応を取ろうとする国です。これも,深刻な飢饉を経験し,多くの人が移民を選ばざるを得なかった歴史的な経験に起因するのではないかと思います。先般,英国のエセックス州でトラックのコンテナから移民を試みたと見られる39人の遺体が見つかるという痛ましい事件がありました。この事件の後,「アイリッシュ・タイムズ紙」のコラムリストのフィンタン・オトゥールは,コラムの中で,「彼らは,少し前の我々だ」と書きましたが,これは,歴史を通じて現在を見ていることを思い起こさせるものです。
アイルランドの注目点の四番目として,「世界における秩序・安定に資する国」ということが挙げられます。最近の世界の状況を考えると,世界における秩序・安定を維持することがますます大きな課題となってきています。そうした中,日本とEUは,世界の秩序・安定を支える主軸の役割を担っており,本年2月に,日本とEUとの間で,経済連携協定,戦略的パートナーシップ協定が発効したことは,大きな意義があると考えられますが,その大きな柱は,「民主主義」「法の支配」「人権」「自由」といった価値と原則の共有です。
ご存知の通り,EUは28カ国の集まりですが,28カ国を個別に見ていくと「秩序・安定に資する」という観点で,さまざまな課題や問題を抱えている国も少なくないのが現状です。そうした中にあってアイルランドは,先に述べたような価値と原則をしっかりと保持・増進する国として重要な役割を果たす国と思います。いくつかの要因がありますが,政治の安定,ポピュリズム的傾向が希薄であること,強いリベラリズム,経済の安定を挙げておきたいと思います。
(アイルランドから見る日本)
これまで「日本から見るアイルランド」を私なりの視点で申し上げてきましたが,今度は,逆に,「アイルランドから見る日本」の方に話題を転じたいと思います。
皆さんもアイルランドの友人の方々と話をされる機会に日本のことをいろいろと聞かれることかと思います。そうした中から,アイルランドの方々が日本についてどのようなイメージを持っているかを感じ取っておられることと思います。
私の受けている感じからすると,キーワード的に申し上げるならば,「経済・技術」「独自の文化」「マンガ・アニメ」といったことが日本のイメージの核の部分を形成してきたのではないかと思います。
一方,アイルランドにとって日本が身近な国かといえば,必ずしもそうではないのが現状と思います。アイルランドにとって身近な国とは,英国であり,米国であり,豪州・カナダであり,スペイン・ドイツ・フランスといったEU諸国なのではないかと思います。日本は,多くのアイルランド人にとって,依然として,「遠い国」「よくわからない国」なのではないかと思います。
そうした意味で,このところ,アイルランドにおいて日本についての関心が増大していることは大変心強いことです。アイルランド政府は2017年7月に「グローバル・フットプリント2025」という政策文書を発表しました。2025年に向けて国際的なプレゼンスを高めていこうというのが大きなテーマですが,全体を貫いている方向性が「東と南へ」ということです。南というのは新興国のことであり,東というのは世界における経済の比重で重要になってきているアジア・太平洋地域のことですが,その中でも,日本が特に重視されています。アイルランド政府は,日本との間で,輸出を増やし,日本からの投資を呼び込み,日本からの観光客を誘致することに並々ならぬ強い関心を持って取り組んでいます。
先般のラグビー・ワールドカップはアイルランドにおける日本への関心を増進させる上で大きな役割を果たしたものと思います。先ほど,日本へのイメージを項目として挙げましたが,今や「ラグビーも意外と強い」といったことも加わったかもしれません。来年には,東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。アイルランドはスポーツ好きの国ですので,また,日本への関心が増す機会となると思います。
このように日本について知ろうとする機運が盛り上がっていることは両国の相互理解の増進を進める大きなチャンスです。皆様にも,ぜひ,彼らの知らない日本を伝えていただければと思います。伝えていただいて意味あることがいくつもあると思います。
一つは,「神話の打破」です。例えば,「日本は物価が高いので,旅行すると高くつく」ということがよく言われます。確かに高級ホテルに泊まって,そこで食事を取り続ければそれなりのお値段がするわけですが,こうした心配をしている人には,日本では安く食事をする方法もふんだんにあることを伝えてあげたいところです。
もう一つは,「点と点を線でつないであげる」ということです。例えば,マンガの面白さにはストーリーの面白さとともに構図の面白さがあるのですが,これは,日本の伝統文化である浮世絵に通じるところがあります。ロボットは先端技術の一つですが,江戸時代にはからくり細工が盛んでした。先端技術やポップ・カルチャーと伝統文化とで繋がっているところがあるのです。
さらにもう一つあげると,「空隙を埋める」と言うことです。縁が薄い国についての知識は一部のことに限られがちです。ぜひ,皆さんには,それぞれの視点,経験から日本のことを紹介していただくことで空隙を埋めていただければと思います。
ラグビー・ワールドカップの開幕の前に,アイルランドの副首相兼外務大臣のサイモン・コーヴニー氏とお会いする機会がありましたが,アイルランドからこの機会に2万5000人が日本に行く予定になっているということを指して,コーヴニー氏は,「2万5000人の大使」と呼んでいました。皆さんにも,ぜひ,アイルランドの友人に日本のことをいろいろとご紹介いただければありがたいと思います。
(将来キャリアに向けて)
最後に,「アイルランド滞在をどのように将来キャリアに生かすか」についてお話ししたいと思います。
将来キャリアといっても,皆さん,それぞれ専攻もさまざまでしょうし,将来キャリアのビジョンもそれぞれのお考えがあると思います。それでも,アイルランドに留学されておられる若い世代の皆さんに共通してお伝えしたいと思っていることをお話ししたいと思います。
私が大学を卒業して,外務省で仕事を始めたのは1980年のことでした,今から約40年前のことです。それから世の中は大きく変わりました。最も大きく変わったことは何かと考えてみると,グローバル化が進んだということと思います。皆さんの時代は,我々の世代やその間の世代の時代に比べてはるかにグローバル化が進んだ時代です。
それでは,グローバル化が進んだ時代に生きていく上で大事な資質は何でしょうか。もちろん,語学も大切と思います。専門分野で優れた知見を持つことも大事だと思います。一方,私は,ここで一つ取り上げるならば,「異なる背景・文化の人々の思考回路を理解する」ということを挙げたいと思います。
皆さんがこれから生きていく世界は,我々の世代が生きてきた世界よりもはるかに「異なる背景・文化の人々」と接しながら生きていく世の中になるでしょう。日本以外の海外が仕事や生活の場となる機会も多いでしょう。また,そうでなくて,仕事や生活の場が日本であっても,外国から来た人と接する機会は多くなるでしょう。日本の会社の職場にも,外国人が普通にいる世の中に向かっていくのではないかと思います。そうした世の中で生きていく上で「異なる背景・文化の人々の思考回路を理解する」ことは極めて重要です。
皆さんにおかれては,ぜひ,アイルランド滞在をアイルランドの人たちの「思考回路」を理解する機会として十分活用していただければと思います。先ほど,「日本から見たアイルランド」についてお話しする中で,「歴史から政策が作られる国」という視点についてお話ししました。これも,アイルランドの人たちの「思考回路」を理解する一つの道筋です。
「異なる背景・文化の人々の思考回路を理解する」ことの有益なところは,応用が利くことです。例えば,アイルランド人の「思考回路」が英国人の「思考回路」と異なっていることが分かれば,世界のいずれの国・地域であっても背景・文化の人々がそれぞれ異なった「思考回路」を持っていることは容易に想像ができます。そうすれば,それぞれの「思考回路」を受け止めること,「思考回路」の違いを認めること,「思考回路」の相違を分かった上で対話を進めることの重要性が理解できます。これらは,グローバル化が進んだ世界で生きていく上でとても大切なことだと思います。
先ほど申し上げたとおり,日本で普通に生活していても,「異なる背景・文化の人々」と接する機会はこれからますます増えていくと思います。一方,Global citizenとして,「異なる背景・文化の人々」と仕事をする道を選ぶのも一つのあり方と思います。皆さんは,海外留学を選ばれた方々なので,皆さんのなかにも,そうした世界に興味と関心を持っておられる方がおられるのではないかと思います。国際ビジネス,NGOもそうした道です。国際機関や外務省で仕事をするのもそうした道です。
「異なる背景・文化の人々」と接するというのは,同じ背景・文化の人と接することに比べてみれば,より難しく,多くの課題にぶつかることです。一方,それだけに,そうした経験から学ぶこと,得ることも多いと思います。皆さんの中で,そうした経験をプラスのものと捉える方が多く出てくることを期待したいと思います。